お知らせ情報インフォメーション
土用明け
2020/11/07
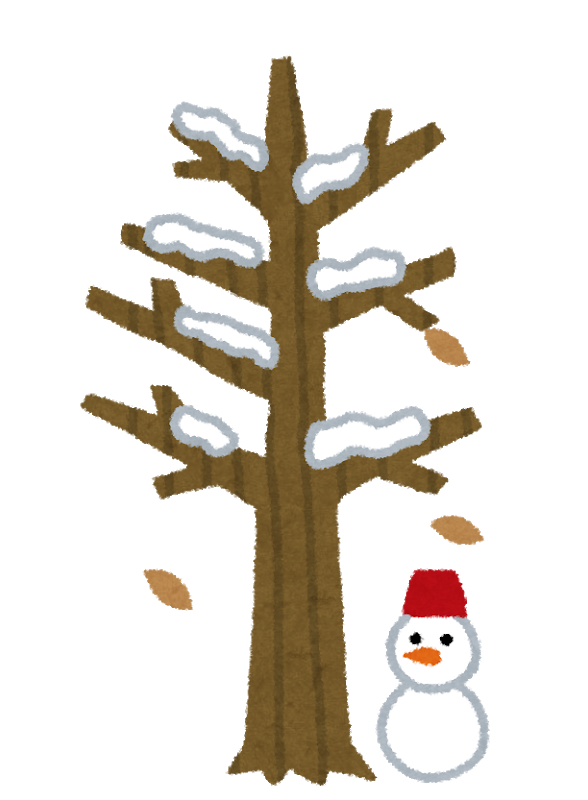
本日は11月7日の土曜日ですが、実は昨日が土用明けでした。
土用についてはこれまでも折に触れて記事にしてまいりましたが、またおさらいしてみたいと思います。
夏の土用の丑の日というのは、どなたも耳にしたことがあるでしょう。
ウナギを食べるのが定番になっている日ですね。
昨今ではウナギは絶滅が危惧されているようで、気軽に口にできる食材ではなくなりつつありますが、やはり土用のイメージというと、まずはウナギなのではないでしょうか。
しかしそもそも土用とは何かというと、「土」という漢字が付いていることが示しているように、土に関係する季節の区切りでした。
中国で五行説というのがありますが、万物の根源にある元素を火・水・金・木・土の五つと見なす考え方です。
いずれも古代天文学で星の名前に使われたりしたようですし、これにお日様とお月様の日月を加えたら、曜日の名前にもなりますね。
ともあれ、あらゆるものはこの五つの元素によって律されていると考えられていたみたいです。
当然、季節というのも五行が司る対象になります。
春が木、夏が日、秋が金、冬が水とそれぞれ対応します。
では土はどこに行ったのかというと、季節と季節の切り替わりの時期が土の影響を受けると見なされました。
そこでそれぞれの季節の合間を土用と呼ぶわけです。
ちなみに各季節の始まりの日を立春とか立冬といいますが、その前日がいわゆる節分です。
豆まきの節分が有名ですが、節分というのは年に四回あるわけです。
で、やはり年に四回ある土用期間が明けるのが、この日になります。
土用明けの何が大事かというと、昔から土用の期間中はあまり土を触るものではないと言われてきたんですね。
土の神様は怖い神様で、土用の間はその神様の気が高まるから、土に手を触れない方がいいということなんだそうです。
お墓の仕事というのは、がっつり土をいじります。
そこで一応われわれも、土用というのを気にしたりするわけです。
さすがに本当に仕事をしないでいると困りますので、必要な作業は行ないます。
昔の人も、実際に土仕事をまったく離れてはいられないと思ったのか、抜け道的なものは用意されていまして、土用中でも間日(まび)と呼ばれる日は土仕事ができますし、また土用前から着手していた作業は、引き続きやっていていいんだそうです。
民間信仰の柔軟さみたいなものが出ていると言えましょうか。
しかしまあそんなわけで、土用を抜けると堂々と土仕事ができる感じになるというか、別に土用だからコソッと作業をするというわけではないのですが、なんとなくホッとします。
そして土用明けということは、今日は立冬。
暦の上ではいよいよ冬となります。
みなさま、体調にはどうかお気を付けください。












