お知らせ情報インフォメーション
埋葬をめぐる用語について
2020/07/27
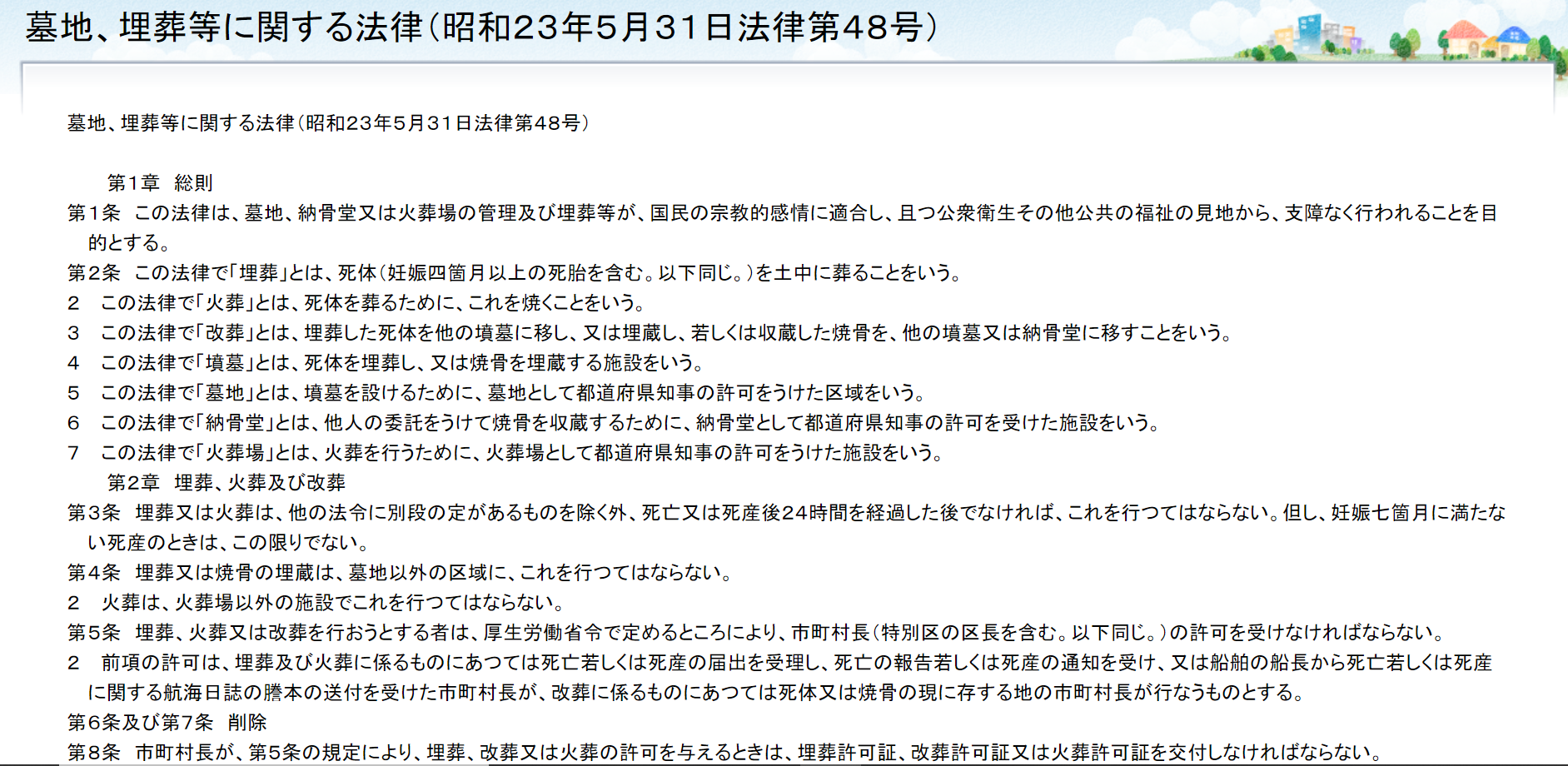
前の記事で、お墓の改葬手続きについて扱ったのですが、その際、主に問題になるのは遺骨の扱いでした。
ところで、その記事の中で、埋葬と埋蔵、さらに収蔵という三つの言葉が使われていました。
実はこれらの言葉、法的にはいずれも別の意味を担っています。
今回はそんな、お骨をめぐる言葉について、ちょっと解説してみたいと思います。
参照する法律は、昭和23年(1948年)に制定されて以来、現在に至るまで、お墓についての唯一の基本的な法律である「墓地、埋葬等に関する法律」、通称「墓埋法」です。
お墓をはじめとするいわゆる祭祀財産については民法、墓荒らしなどの犯罪についてはもちろん刑法に個別の規定はありますが、墓地の管理や運営についての総合的な法律は墓埋法だけです。
で、この法律の第2条に「埋葬」についての定義があります。
そのまま引用してみます。
「第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。」
第2条の1項、4項、6項を引用しましたが、いろいろな言葉が出てきました。
「墳墓」というのは、要するにわれわれがイメージする普通の「お墓」を指す法律用語です。
この「墳墓」を設けるために、特別の許可を受けた区域が「墓地」です。
「納骨堂」というのは、主にお寺にあるのが想像されるかと思いますが、骨壺を預かる施設、と表現して差し支えないかと思います。
以上を整理するとはっきりしますが、まとめますと、「墳墓」に遺体を土葬することが「埋葬」、「墳墓」に火葬された遺骨を納めることが「埋蔵」、「納骨堂」に遺骨を預けることが「収蔵」という使い分けがあります。
もちろん、日常にはほとんど関わりのない区別ではあります。
というか多くの方にとって、火葬されたお骨をお墓に納めることが埋葬することだ、というイメージなんじゃないかと推測されます。
普通に言葉を使う分には、それで問題が生じるはずもありません。
法律上、このような言語体系になっている理由は、やはり古い法律であるということが一番に挙げられるでしょう。
戦後に制定されたとはいえ、当時はまだ地方によって土葬も多い時代でしたし(といっても都市部での火葬率は相当高くなってはいました)、そもそもこの法律自体、明治17年の「墓地及埋葬取締規則」を下敷きにしているものです。
まあ法律用語ってのはそんなものだ、と言ってしまえばそうですし、古い法律であることが悪いわけでもありません。
問題があるとすれば、法律の中身がまったくアップデートされず、エンディングの多様化と言われる現状をまるでカバーできていないことでしょう。
誰もがお墓を持って、そこに葬られることを前提としているため、手元供養や散骨についての規定は皆無です。
そもそもこの法律は、死者は埋葬(ないし火葬して埋蔵)されねばならない、という規定を持っておらず、これは世界的にも例外的なことだと聞きます。
たとえば散骨が悪いことだとまで申しませんが、死生観というのは文化の一部ですので、現状を踏まえて一度法を整備し直すべきだとは思うのです。
テーマが少しそれてしまいましたが、今回は「埋葬」をめぐる用語から、墓埋法について、でした。












