お知らせ情報インフォメーション
「お墓の文化論」第二回
2016/10/29
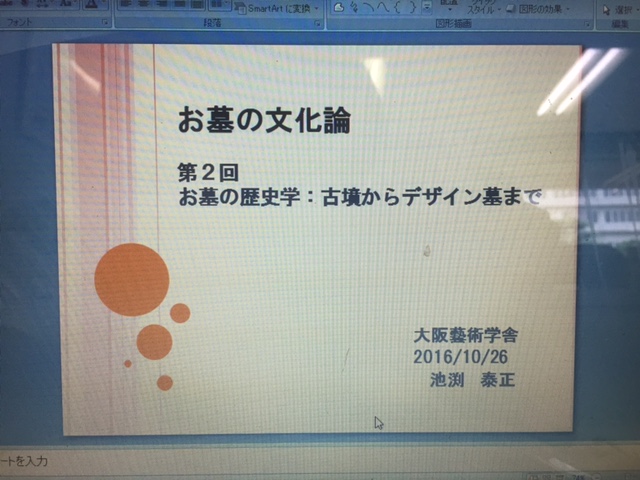
一昨日に引き続き、「お墓の文化論」のお話をさせていただきます。
藝術学舎という一般向けの公開講座がありまして、私はお墓を社会文化的な視点から見るというテーマで、ひとつの講座を担当させてもらっています。
その第二回目の講義が今週の水曜日にあったのです。
いや、夕方に雨が降るという予報は知っていたのですが、ちょうど私が家を出ようかという直前からザンザン降りになりまして、濡れましたねえ。。
歩いている最中に、やけに傘を持つ手に水がしたたってくるから、何事ぞと思って見上げると、傘のてっぺんあたりに小さな穴が開いているという。
そりゃ濡れますよ……。
ところで今回も、会場である大阪富国生命ビルの写真を撮ってくるのを忘れました。。
藝術学舎を主宰する京都造形芸術大学のサテライトキャンパスが、その五階にあるのですが、梅田東の超一等地で、賃貸料はいったいいくらくらいするんだろう、なんて下世話なことをついつい考えてしまいますね。
きれいなビルです。
本題に戻りましょう。
昨日は「お墓の歴史学」というテーマで喋ってきました。
詳しい内容については、すべての講座が終わってからあらためて、当ブログにてまとめたいと思いますが、要は現代に至るまでの葬墓制の歴史的な変遷についてですね。
しかし何と言いますか、やはり「古墳からデザイン墓まで」というサブタイトルは無茶でしたね。。
古墳どころか先史時代から扱ってしまったわけですが、二時間の枠では現代まで辿り着けませんでした。
いや、これはまったく私の無計画ゆえなのですが、平安から室町末期、いわゆる日本中世の葬墓制の変化なんかを見ていくと非常に面白いんですね。
とりわけ南北朝から室町にかけて、日本社会の編成に重大な転換があったというのは、歴史家の網野善彦さんなんかも指摘しておられることですし、鎌倉新仏教の成立から展開ということも含めて、死をめぐる社会文化も大きく変化していきます。
そんなことに力を入れて話していると、江戸時代まで終えたところで時間が来てしまった、と。。
まあこれはある意味でキリがいいというか、明治以降というのは墓地に関する法律なども整備され、現代に直接結びつく墓地行政や葬墓文化が成立していく時期になります。
次回の講義は「お墓の法・社会・経済学」というテーマを予定していますが、お墓の現代的なあり方を概観する中で、明治以降の歴史的経緯も盛り込んでいこうと、こんな風に思っています。
一応は前向きと言いますか……。
いや、毎回のテーマを時間内で終わらせられるのが一番なんですけどね。
ともあれ次は時間内できちんとまとめられるよう、準備していきたいと思います。












