お知らせ情報インフォメーション
霊標の種類について
2019/05/28
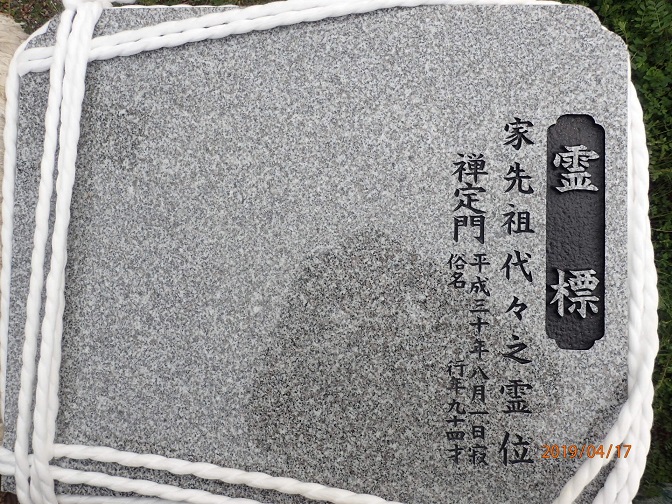


少し前の記事で、新しい霊標を設置する工事について取り上げました。
その際、霊標にもいろいろな種類があるということを申し上げました。
大きさにいろいろあるのはもちろんなのですが、ここで取り上げたいのは、霊標を支える台石についてです。
まず基本ですが、霊標というのは亡くなった方のご戒名(浄土真宗では法名)、生前のお名前、没年月日、没年齢などを彫り入れる、板状の石です。
衝立のようにしてお墓の脇に置かれることが多いです。
墓誌と呼ばれることもありますし、浄土真宗では法名碑ということが多いです。
石でできた過去帳、という風にご理解していただいて差し支えないかと思います。
具体的には写真一枚目のようなものですね。
これに台を付けて、墓所区画の内側に設置するわけですが、この台石には大きく分けて二つの種類があります。
「下駄タイプ」と「はめ込みタイプ」と呼んでおくことにします。
弊社で施工事例が多いのは、下駄タイプのものです。
しかし下駄、とだけ連呼しててもイメージがつかみにくいかと思いますので、実際のものをご覧いただきましょう。
写真二枚目です。
板石の上に、霊標を支える一対の台が乗っています。
これが履物の下駄を連想させるので、霊標の下駄(台)と呼ばれるわけです。
下駄の中心から突き出ているのは、ステンレスの芯棒です。
下の板石にも穴が開けられて、この芯棒は地面まで刺さっています。
霊標本体にも位置を合わせて穴が開いていて、これを通して設置することになります。
霊標は大きな石ですので、自重で安定しますが、さらに少しでもこけにくくするための工夫です。
奈良の弊社近隣地域では、昔からこのタイプの霊標が多く、今でも下駄式が主流と言っていいと思います。
もうひとつのはめ込み式というのは、文字通り霊標をはめ込めるような台石を用意するものです。
具体的には写真三枚目のようなものです。
石塔の向かって右側に置かれているのがそうです。
ここに直接、霊標本体をはめ込むように設置します。
下駄式よりも幅を小さくできますので、スペースのないところにも置きやすいです。
こちらの場合、中央に開いている穴は、芯棒を通すものではなく、水抜き穴です。
石を刳ったところに水が溜まってしまうと大変ですので、雨など降っても水が溜まらず流れていくようになっています。
どんな霊標を置くにしても、まずはお施主さんのご要望がありましたら、そちらに耳を傾けますし、現場を拝見してどのようにするのがよいか、こちらから提案もさせていただきます。
基本的な形状というのはございますが、規格品をストックしているわけではなく、その都度その都度のオーダーメイドですので、サイズやデザインなどもご希望に沿うことができます。
お墓はその家の歴史を語る場所、とよく申しますが、霊標を置くと、そのお墓にお祀りされているご先祖様たちが一目瞭然になり、いいものじゃないかな、とも思いますね。
今回は霊標についてのご案内でした。












